「Diagnosis Procedure Combination / Per-Diem Payment System」の略で、入院患者様の病名や診療内容の組み合わせに基づき、厚生労働省が定めた1日あたりの包括点数『診断群分類(DPC)に基づく1日あたり包括払い制度(PDPS)』から入院医療費を計算する制度のことです。
当院ではDPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた病院情報を作成し、一般市民の皆様に、当院の特徴や急性期医療の現状を理解していただくことを目的として、病院情報の公表を行なっています。
また、病院の様々な機能や診療の状況などを具体的に数値化し、客観的に評価・分析することで医療サービスの質の向上を図っています。
公表している情報(指標)は、令和6年度(令和6年6月1日から令和7年5月31日)に退院された患者様のデータを対象として集計しています。
尚、DPCの制度上、次に該当される患者様は集計の対象とはなりません。
① 健康保険証を使用されない(自動車損害賠償責任保険や労災保険、自費など)患者様のデータ
② DPC対象外病棟(地域包括ケア病棟)のみに入院された患者様のデータ
| 在院日数 | 当院に入院していた(入院日から退院日まで)日数です。 |
|---|---|
| 患者数 | 1回の入院を1カウントしています。 |
| 平均年齢 | 入院日の年齢の平均値です。 |
| 転院率 | 該当する項目の症例数のうち、当院から他の病院へ転院(継続入院)された患者様の割合です。 |
| -(ハイフン) | 患者数が10未満の場合には「-」としています。 |
1 病院指標
- 1) 年齢階級別退院患者数
- 2) 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3) 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4) 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5) 脳梗塞の患者数等
- 6) 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 7) その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
2 医療の質指標
病院指標
退院患者さんの人数を10歳刻みの年齢階級別に集計しています。

| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 48 | 230 | 189 | 262 | 380 | 487 | 510 | 427 | 136 |
14桁のDPCコード(診断群分類番号)について、各診療科別に集計しています。
項目は、DPCコード(診断群分類番号)に対する患者数、平均在院日数(自院・全国)、転院率、平均年齢、患者用パスの有無で、各診療科別に上位5つを掲載しています。
【用語について】
| DPCコード |
DPCでは、入院の患者さんの病名と治療内容(手術や処置など)の組み合わせにより3,248種類(令和6年度)の診断群に分類され、それぞれに14桁のDPCコード(診断群分類番号)が割り振られています。 このコードは、病気と治療内容によって分類されますので、同じ病気であっても治療方法が違えばDPCコードは異なります。 |
|---|---|
| DPC名称 | どのような病気で、どのような治療内容を行ったかを表しています。 |
| 平均在院日数(自院) | 当病院に入院していた日数(入院日から退院日までの日数)の平均値です。 |
| 平均在院日数(全国) | 厚生労働省より公表される令和6年度における全国のDPC対象病院の在院日数の平均値です。 |
| 患者用パス | ある一定病気に対して、治療・検査・処置などの内容をスケジュール表(パス表)にまとめ、治療内容を標準化した「治療計画表」のことです。治療時に患者さんにお渡し、説明を行っております。また、患者用パスが存在するものについては、患者用パスを掲載しています。 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060335xx02000x | 胆石性胆のう炎等の腹腔鏡下胆のう摘出術 | 319 | 6.10 | 7.05 | 0.00% | 55.43 | 腹腔鏡下胆のう摘出術 |
| 060160x001xxxx | 15歳以上の鼠径ヘルニアの腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 291 | 3.12 | 4.54 | 0.34% | 63.12 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 |
| 060340xx03x00x | 胆管結石、胆管炎 内視鏡的胆道結石除去術等手術 | 61 | 4.26 | 8.88 | 1.64% | 71.95 | - |
| 170020xxxxxx0x | 急性アルコール中毒の治療 | 48 | 1.27 | 2.98 | 0.00% | 29.21 | - |
| 080240xx97xxxx |
多汗症の手術 |
44 | 1.23 | 3.04 | 0.00% | 27.93 | 多汗症手術 |
身体への負担を可能な限り軽く、社会復帰を1日でも早くできるよう、鏡視下手術を積極的に採用し、術後の早期回復、早期退院に努めていることが平均在院日数に数字として顕著に表れています。
外科で最も症例の多い胆石性胆のう炎等では、従来はお腹に4カ所の小さな穴を開けて腹腔鏡下胆のう摘出術を採用していましたが、2009年より1ヵ所の小さな穴を開けて行う単孔式腹腔鏡下胆のう摘出術を採用し、更なる低侵襲を実現しました。
また、平成10年より開始した日帰り手術では鼠径ヘルニア、多汗症などかなりの症例数を誇り、当診療科の2位、5位となっています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070350xx02xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術(後方摘出術) | 71 | 19.58 | 13.83 | 2.82% | 46.31 | 腰椎手術 頚椎手術 |
| 070343xx97x0xx | 腰部脊柱管狭窄症・脊椎すべり症の手術 検査・ブロックなし | 55 | 24.76 | 15.41 | 5.45% | 72.00 | 腰椎手術 |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 54 | 39.76 | 25.29 | 38.89% | 82.67 | 大腿骨頚部骨折手術(人工骨頭・骨接合) |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性含む)の人工関節置換術 | 35 | 35.77 | 21.38 | 0.00% | 74.66 | 人工膝関節全置換術/人工単顆置換術 |
| 070343xx97x1xx | 腰部脊柱管狭窄症・脊椎すべり症の手術+脊髄造影(ミエログラフィー)検査 | 35 | 22.14 | 20.75 | 0.00% | 69.31 | 腰椎手術 |
当診療科は脊椎・脊髄手術を強みとし、第1位の椎間板ヘルニアに対する椎弓形成・ヘルニア摘出術・後方固定術の症例が最も多く、腰部脊柱管狭窄症及びすべり症に対する椎弓形成手術が第2位、第5位となっています。膝・肩といった関節疾患にも注力しており、膝の人工関節置換術が第4位となっています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 大腸良性腫瘍(大腸腺腫・大腸ポリープ)の内視鏡的手術 | 187 | 2.20 | 2.57 | 0.53% | 63.87 | 大腸ポリペクトミー・EMR |
| 060102xx99xxxx | 大腸憩室炎・憩室出血等(穿孔又は膿瘍を伴わない)の治療 | 56 | 5.50 | 7.60 | 0.00% | 56.71 | - |
| 060380xxxxx0xx | 感染性(ウイルス性)腸炎の治療 | 55 | 3.78 | 5.55 | 0.00% | 46.20 | - |
| 170020xxxxxx0x | 急性アルコール中毒の治療 | 47 | 1.32 | 2.68 | 0.00% | 32.43 | - |
| 060210xx99000x | 腸閉塞(イレウス)の治療 | 22 | 6.64 | 9.08 | 0.00% | 76.55 | - |
消化器内科では、大腸良性腫瘍の内視鏡的手術が最も多くなっています。
また検査・治療を行う内視鏡センターにはカプセル内視鏡や経鼻内視鏡、超音波内視鏡など各種ハイビジョン高画質タイプの器具を揃え、早期発見できる体制を整えています。
目指すのは「早期発見・早期治療」。
当診療科で対応が難しいがん等については、外科で対応する体制となっています。
また当診療科では、消化管全体の炎症や感染症、出血などの緊急患者さんの受け入れを行っているため、その症例数が第2位、第3位となっています。
4番目の疾患については、当院が救急指定病院であること、都市部に立地しているためと考えられます。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170020xxxxxx0x | 急性アルコール中毒の治療 | 12 | 1.33 | 2.68 | 0.00% | 29.00 | - |
前述のとおり、急性アルコール中毒の患者さんを多く受入れているため、当診療科で第1位となっています。また、上記データには反映されていませんが、心不全の患者の症例数が第2位となっています。
他の病院と連携をとり、リハビリ等の治療が必要な患者さんを受け入れ、患者さんが1日も早く社会復帰できるようスタッフ一丸となり取り組んでいます。
心不全が悪化した緊急の患者さんの受け入れも行っています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170020xxxxxx0x | 急性アルコール中毒の治療 | 18 | 1.17 | 2.68 | 0.00% | 26.11 | - |
前述のとおり、急性アルコール中毒の患者さんを多く受入れているため、当診療科で第1位となっています。当院では平成28年4月に「肝臓内科」を新設し、軽度の肝障害から慢性肝炎、肝硬変、肝がんの肝臓病の全般の治療ができるようになりました。また、平成29年4月より肝疾患専門医療機関の指定病院となっています。
肝臓内科では、非代償性肝硬変の患者さんを多く受入れています。また、内視鏡的治療や肝切除等が必要な場合には、消化器内科や外科で対応できる体制を整えています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170020xxxxxx0x | 急性アルコール中毒の治療 | 15 | 1.67 | 2.68 | 0.00% | 28.07 | - |
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン注射による治療あり(教育入院) | 11 | 15.64 | 13.77 | 0.00% | 65.36 | - |
前述のとおり、急性アルコール中毒の患者さんを多く受入れているため、当診療科で第1位となっています。糖尿病内科では、2型糖尿病に対するインスリン治療(教育入院)も積極的に行っており、その症例数が第2位となっています。
また、当院では令和1年6月に「糖尿病内科」を新設し、これまでの通院治療に加え、専門的な糖尿病の入院治療もできるようになりました。
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんの人数を、初発のUICC病期(ステージ)分類別、および再発に分けて集計しています。
この指標の患者数は、延患者数となります。同じ患者さんが複数回入院された場合、入院期間ごとの数で患者数を集計しています。
また、ステージが「0」のものについては集計対象外としています。
■UICC病期分類・・・国際対がん連合(UICC)によって定めたTNM分類(T:原発巣の大きさと進展度、N:所属リンパ節への転移状況、M:遠隔転移の有無の分類)によって、各がんの病期(ステージ)を5つに分類しています。
| がんの病期(ステージ)分類 | |
|---|---|
| Stage0 | 上皮内がん |
| StageⅠ | 原発臓器に限局するがん |
| StageⅡ | |
| StageⅢ | 局所進展するがん、特に所属リンパ節に転移を有するがん |
| StageⅣ | 遠隔転移を有するがん |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 6 | - | 1 | 5 | - | 7 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 14 | 18 | 27 | 13 | 1 | 27 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 18 | 20 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
当院では胃癌・大腸癌は外科・消化器内科、乳癌・肺癌は外科、肝癌は外科・肝臓内科で治療を行っています。
StageⅠについては消化器内科にて、内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)により、早期治療を目指します。内視鏡での治療が難しい症例は、外科を中心に手術・化学療法・緩和ケアなどの選択肢の中から患者さんの状態にあった、希望に沿った治療を組み合わせて行っています。
再発癌については、がん専門病院と連携し、多くの進行再発癌の患者さんを受け入れています。
乳癌については、平成28年9月より専門クリニックと新たに連携したことを契機に症例数を伸ばしています。
成人(18歳以上)の市中肺炎(※1)の患者さんについて重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計しています。
重症度は、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類を用いて分類しています。
この指標では、「入院のきっかけとなった傷病名」と「最も医療資源を投入した傷病名」が肺炎の患者さんを集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルス肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、急性気管支炎、小児肺炎などは集計対象外としています。
※1 市中肺炎とは、病院外で日常生活をしていた人に発症した肺炎です。
| 肺炎の重症度分類 | 治療の場との関係 |
|---|---|
| 軽症 | 外来治療レベル |
| 中等症 | 外来または入院レベル |
| 重症 | 入院レベル |
| 超重症 | ICU入院レベル |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 13 | 7.38 | 46.00 |
| 中等症 | 17 | 15.88 | 79.88 |
| 重症 | - | - | - |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
患者数が最も多いのは中等症の患者さんとなっています。
軽症の平均年齢が40歳代に比べ、中等症は平均年齢が80歳前後と高齢になっており、成人市中肺炎は高齢になるほど重症化してい ることが分かる結果となりました。
成人市中肺炎診療ガイドラインでは、軽症の患者さんは外来治療となっておりますが、癌などの既往があったり、他疾患の併発・合併が懸念される場合など、重症化が危惧され入院となるケースもあります。
なお、この指標にありませんが、当院では、主に内科で肺炎の患者さんの緊急受け入れを行っています。
脳梗塞の分類にあたる患者さんについて、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しています。
この指標では、「最も医療資源を投入した傷病名」が脳梗塞のICD-10 I63$に該当した患者さんを集計しています。
※ICD(国際疾病分類)とは、正式な名称を「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」といい、疾病、傷害及び死因の統計を国際比較するためWHO(世界保健機関)から勧告された統計分類のことです。ICDはアルファベットと数字を用いコード化されたものであり、コードによってその病名が表されています。現在、わが国ではWHOによる第10回目の改訂版「ICD-10」に基づき、傷病名の統計分類を行っています。
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
当院には脳神経外科や神経内科等が無いため、専門的な治療が必要な患者さんは、基本的に他の医療機関へご紹介させて頂きます。ただし、患者さんが当院での治療を強く希望された場合は、連携している専門医の指示・協力を仰ぎ、当院にて治療させて頂くこともあります。
こうした場合に備え、平素より他院との連絡を密にとり、スピーディーに判断、対応できる体制作り、連携に取り組んでいます。
手術件数が多い順に上位5手術(Kコード)について、診療科別に集計しています。
項目は、手術(Kコード)に対する患者数、平均術前日数、平均術後日数、転院率、平均年齢、患者用パスの有無を掲載しています。
入院中に複数の手術を行った場合については、主たる手術(又は点数の最も高い手術)のみをカウントし、集計しています。
輸血関連(K920$)や創傷処理、非観血的整復術、徒手整復術等の軽微な手術や加算等については集計から除外しています。
【用語について】
| Kコード | 医科の診療報酬点数表で定めた、手術に対する点数表コードのことです。 |
|---|---|
| 名称 | 手術術式の名称です。 |
| 平均術前日数 | 入院日から手術日まで(手術日当日は含まない)の平均日数です。 |
| 平均術後日数 | 手術日から(手術日当日は含まない)退院日までの平均日数です。 |
| 患者用パス | ある一定病気に対して、治療・検査・処置などの内容をスケジュール表(パス表)にまとめ、治療内容を標準化した「治療計画表」のことです。治療時に患者さんにお渡し、説明を行っております。また、患者用パスが存在するものについては、患者用パスを掲載しています。 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 373 | 1.17 | 4.57 | 0.54% | 56.64 | 腹腔鏡下胆のう摘出術 |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 291 | 0.11 | 2.02 | 0.34% | 63.12 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 |
| K196-2 | 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) | 44 | 0.14 | 0.09 | 0.00% | 27.93 | 多汗症手術 |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 35 | 0.74 | 2.83 | 0.00% | 32.14 | 腹腔鏡下虫垂切除術 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 31 | 0.45 | 4.65 | 6.45% | 72.32 | - |
前述の通り、1位は胆のう疾患に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術となっています。
鼠径ヘルニアについては、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(TAPP) が第2位となっています。
また第3位は多汗症に対する手術であり、平均術前日数0.14平均術後日数0.09日に表れているようにほぼ日帰り手術で行っています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 169 | 3.38 | 19.07 | 3.55% | 62.41 | 腰椎手術 頚椎手術 |
| K0821 | 人工関節置換術(膝)(股)(肩) | 60 | 2.37 | 33.22 | 5.00% | 74.52 | 人工膝関節全置換術/人工単顆置換術 |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 55 | 7.82 | 27.16 | 5.45% | 69.87 | 腰椎手術 |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿)(上腕) | 34 | 2.47 | 35.94 | 32.35% | 79.79 | 上肢骨折手術 下肢骨折手術 |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 25 | 2.80 | 34.80 | 40.00% | 82.72 | 大腿骨頚部骨折手術(人工骨頭・骨接合) |
整形外科では、脊椎疾患(脊柱管狭窄症、すべり症、ヘルニア、脊髄症、後縦靱帯骨化症等)の患者さんが多く、手術件数も同様に脊椎疾患に対する「椎弓形成術」が最も多くなっています。
当診療科第2位の人工関節置換術は、「膝」が36件、「股」14件、「肩」10件となっており、膝の疾患については、変形性膝関節症に対する人工関節置換術が最も多くなっています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 164 | 0.20 | 1.01 | 0.00% | 64.32 | 大腸ポリペクトミー・EMR |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 22 | 0.18 | 1.00 | 0.00% | 63.36 | 大腸ポリペクトミー・EMR |
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 15 | 0.93 | 5.67 | 0.00% | 69.20 | 大腸ESD |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 13 | 0.92 | 2.38 | 7.69% | 53.38 | - |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12 | 0.17 | 9.00 | 0.00% | 61.17 | - |
前述のように内視鏡治療に注力しているのが分かる結果となっています。
大腸良性腫瘍に対する内視鏡的粘膜切除術(EMR)が第1位、第2位、早期大腸がんに対する早期悪性粘膜下層剥離術(ESD)が第3位、上記データには反映されていませんが、早期胃がんに対する早期悪性粘膜下層剥離術(ESD)が第6位となっています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 11 | 1.45 | 8.64 | 0.00% | 73.55 | - |
肝臓内科では、腹水濾過濃縮再静注法(CART)の治療が必要な 難治性腹水を呈した肝硬変症の患者さんを積極的に受け入れていることが分かる結果となっています。
「最も医療資源を投入した傷病名」が播種性血管内凝固症候群(DIC)、敗血症、真菌感染症、手術・術後等の合併症について、患者数と発生率を集計しています。また、「最も医療資源を投入した傷病名」と「入院契機(入院のきっかけとなった傷病名)」が、「同一」か「異なる」かで分類し 集計しています。
【用語について】
| 播種性血管内凝固症候群(DIC) | 重篤な感染症や悪性腫瘍などの様々な基礎疾患を原因として起こる、全身性の重篤な病態のことです。 |
|---|---|
| 敗血症 | 感染症によって起こる全身性炎症反応の重篤な状態です。 |
| 真菌感染症 | 真菌によって起こる感染症です。 |
| 手術・処置等の合併症 | 手術や処置などに一定割合で発生してしまう病態です。術後出血や創部感染症などが挙げられます。合併症はどのような術式でもどのような患者さんでも一定の割合で起こり得るもので、医療ミスとは異なります。 |
| 入院契機 | 入院のきっかけとなった傷病名「入院契機病名」のことです。 |
| 発生率 | 全患者数のうち、該当疾患を発症された患者さんの割合です。 |
| 入院契機が「同一」・「異なる」 | 入院契機が「同一」の場合は、ある病気の治療目的で入院し、その病気の治療を行ったことを表します。(例:合併症等を既に発症した状態で入院し、当院で治療。) |
| DPC6桁 | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - |
播種性血管内凝固症候群や敗血症は、DPCで高額な点数が設定されているため、臨床的に根拠のある診断でなければアップコーディング(不適切な入院医療費請求)と疑われるものとされています。
当院では臨床的に根拠のある診断を基に 診療内容(医療資源)も勘案した上で、DPC病名の決定、入院医療費請求を行っています。
当院で播種性血管内凝固症候群や敗血症等を傷病名としたケースは、10症例未満という結果となりました。
手術・処置等の合併症については、他医療機関で手術を行い、術後に合併症を発症された患者さんの紹介を積極的に受け入れているため、発生率が0.22%となっています。特に当院では、内視鏡手術後の術後出血の患者さんや、透析シャントトラブル術後の患者さんがいらっしゃいます。
医療の質指標
リスクレベルが「中」以上の手術の実施と 肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者について、患者数と実施率を集計しています。
【用語について】
| 肺血栓塞栓症 | 肺血栓塞栓症は、以前、「エコノミークラス症候群」として有名となった疾患です。 「エコノミークラス症候群」は、飛行機の狭い座席で長時間安静にしていると主に下腿に血栓ができ飛行機から降りて歩行した時、血栓が剥がれ血流に乗って 肺へと移動して肺の血管に詰まり、様々な症状が起こる病態です。これと同様に、手術前後は安静を必要とし、その上特に術後には血液の固まりやすい状況が起ります。近年、肺血栓塞栓症の危険因子が明らかになっており、危険因子レベル(リスクレベル)に応じた予防対策を行うことが大変重要であるとされています。 |
|---|---|
| 予防対策 (方法と実施の対象) | 予防対策の方法には、弾性ストッキングの着用や間歇的空気圧迫装置の使用、抗凝固療法等があります。 これらの方法の実施は、ガイドラインに則り、手術のリスクレベルに「付加的な危険因子(付加的リスク)」を加味して総合的に判断し、最終的なリスクレベルが「中」「高」となった患者さんが対象となります。 |
| 実施率 | リスクレベル「中」以上の手術を施行した患者のうち、予防対策を実施した患者さんの割合です。 |
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、 肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
| 768 | 749 | 97.53% |
周術期(術前・術中・術後)に肺血栓塞栓症の予防対策を実施することは、肺血栓塞栓症の発生率を下げることに繋がるため、医療の質向上のために予防対策の実施率を上げていくことが求められています。
当院の実施率は97.53%という結果となりました。査定等の影響で上記データには反映されておりませんが、当院では「肺血栓塞栓症/深部静脈血栓症(静脈血栓塞栓症)予防ガイドライン」に則り、インフォームド・コンセントから予防対策実施まで、より良い医療が提供できるよう積極的に予防対策を行っています。
血液培養の実施と 血液培養を2セット実施したものについて、日数と実施率を集計しています。
【用語について】
| 血液培養 | 血液培養は、本来無菌である患者さんの血液から病原体である起炎菌(細菌や真菌など)を検出・培養する検査のことです。 敗血症などの血流感染症の診断に用いられ、早期診断と適切な治療方針の決定、感染源の起炎菌を特定することができます。 |
|---|---|
| 2セット実施 | ガイドラインにおいて、血液培養2セット以上の採取(実施)が推奨されています。 その理由として、血液中の菌量は非常に少数であり、2セット採取することで血液採取量が増え 起炎菌検出率が向上すること、また、皮膚常在菌が検出された場合にコンタミネーションの判断をするために2セット以上の採取が推奨されています。 |
| 実施率 | 血液培養のオーダー実施日数のうち、血液培養のオーダーが1日に2件以上実施された日数の割合です。 |
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
| 151 | 128 | 84.77% |
当院での血液培養2セット実施率は84.77%という結果となりました。
ガイドラインに基づき、血液培養2セット以上の実施を原則としていますが、血管の確保が難しいなどの理由により、患者さんの状況に応じて1セットのみ実施する場合があります。
広域スペクトル抗菌薬の使用と その使用日までの間に細菌培養(細菌培養同定検査)が実施された患者について、患者数と実施率を集計しています。
【用語について】
| 広域スペクトル抗菌薬 | 菌のタイプによって、効果のある抗菌薬は異なります。効果のある菌の範囲を「スペクトル」といいます。 抗菌薬の中でも、複数の菌タイプに有効なものは、広い範囲の菌に効果があるとして「広域スペクトル抗菌薬」と呼ばれています。 |
|---|---|
| 細菌培養(細菌培養同定検査)の実施 | 近年、多剤耐性アシネトバクターなど、新たな抗菌薬耐性菌(以下、耐性菌)が出現し、難治症例の増加が世界的にも問題となっています。 不適切な抗菌薬の使用は、耐性菌の発生や蔓延の原因になることから、抗菌薬適正使用の推進が求められています。その鍵を握るのは正確な微生物診断であり、抗菌薬使用前の適切な検体採取と細菌培養同定検査の実施が必要であるとされています。 |
| 実施率 | 広域スペクトル抗菌薬を使用(処方)した患者のうち、入院から抗菌薬使用日(処方日)までの期間に細菌培養同定検査が実施された患者さんの割合です。 |
| 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
| 44 | 33 | 75.00% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率は75.00%となりました。 当院では院内感染対策チーム(ICT)を組織し、院内感染の防止のため様々な活動を行っています。 抗菌薬については全ての種類の使用状況を把握するとともに ICTが指定する抗菌薬の使用の際には、細菌培養同定検査の実施の確認及び促進をするなど、耐性菌発現防止のための抗菌薬適正使用の推進にも取り組んでいます。 また、感染対策連携共通プラットフォームに参加し、耐性菌の発現を把握した際には状況を報告・共有しています。
入院中に転倒・転落が発生した患者さんについて、転倒・転落件数と発生率(‰)を集計しています。
この指標の転倒・転落件数は、発生件数となります。同じ患者さんが複数回 転倒された場合、転倒ごとの数で集計しています。
【用語について】
| 転倒・転落 |
入院中は、環境の変化や治療・リハビリの影響により、自分の意思とは関係なく、つまずきやよろめきによる転倒(転ぶこと)や転落(段差のあるところから落ちること)のリスクが高まります。 もし転倒・転落によって骨折等が発生した場合、患者さんのQOL(生活の質)の低下だけでなく、在院日数の延長や医療費の増加にもつながります。 そのため、転倒・転落を防ぐための環境整備や職員への教育等、様々な対策を講じて患者さんの安全確保に努め、万が一転倒が起きた場合にも、外傷を最小限にとどめられるような工夫や対応が求められています。 |
|---|---|
| 発生率(‰) | 入院患者延べ数のうち、転倒・転落が発生した件数の割合で、その単位を‰(パーミル)としています。 ‰(パーミル)は、入院患者1000人あたり何件(何人) 転倒・転落が発生したかを表しています。 |
| 退院患者の在院日数の総和もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 転倒・転落発生率 |
| 30030 | 77 | 2.56% |
当院では、転倒・転落のリスクを軽減するため、転倒・転落防止器の活用やスタッフ間の連携強化などを通じて、患者さんが安全で快適な入院生活を送れるよう、未然防止に努めています。
しかしながら、転倒・転落事故を完全に防ぐことは難しく、転倒・転落発生率は2.56‰(パーミル)という結果になりました。
万が一、事故が発生した際には、速やかかつ適切な対応を行い、患者さんの安全と安心を最優先に努めてまいります。
転倒・転落が発生した中でインシデント影響度分類レベル3b以上の事例について、件数と発生率(‰)を集計しています。
■インシデント影響度分類 及び、損傷レベル分類
| インシデント影響度分類 | 損傷レベル分類 | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル | 傷害の継続性 | 傷害の程度 | ||
| レベル0 | - | なし | 未然に防ぐとこができた又は、患者さんには変化がなかった場合 | |
| レベル1 | なし | |||
| レベル2 | 一過性 | 軽度 | 軽度 | 観察が必要となったが、治療の必要が無かった場合 |
| レベル3a | 一過性 | 中等度 | 中程度 | 一時的な治療が必要となった場合 |
| レベル3b | 一過性 | 高度 | 重度 | 手術、骨折など、継続的・濃厚な治療が必要となった場合 |
| レベル4a | 永続性 | 軽度~中等度 | ||
| レベル4b | 中等度~高度 | |||
| レベル5 | 死亡 | 死亡 | ||
【用語について】
| インシデント影響度分類レベル3b以上 | インシデントが発生した場合は、「インシデント影響度分類」に基づいてレベル分類を行っています。 このうちレベル3b以上とは、転倒・転落などにより、継続的かつ濃厚な治療が必要となった事例(有害インシデント)を指し、損傷レベル分類では「重度」以上のレベルに位置づけられます。 発生事例に対しては追跡調査や原因分析を行い、そこから導かれた予防対策を実施することによって、転倒・転落による損傷の低減や予防につなげています。 |
|---|---|
| 発生率(‰) | 入院患者延べ数のうち、インシデント影響度分類レベル3b以上の発生件数の割合で、その単位を‰(パーミル・千分率)で表しています。 |
| 退院患者の在院日数の総和もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 |
| - | - | - |
転倒・転落の原因は様々ですが、高齢になるにつれ、筋力やバランス感覚の低下などの身体的機能低下に伴い転倒リスクが高まります。また、高齢者にとっての転倒・転落は骨折や頭部外傷等の大けがにつながりやすく、それが原因で寝たきりなど介護が必要な状態になることもあります。
当院の転倒・転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生件数は10症例未満であり、発生率は0.30‰(パーミル)となっています。
上記データには反映されておりませんが、3b以上の事例の平均年齢が80.5歳と高齢になるほど転倒リスクが高まることが分かる結果となりました。
手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬の投与が開始された手術について、件数と投与率を集計しています。
【用語について】
| 予防的抗菌薬投与 | 現在、細菌感染症を起こしていない患者さんに対して、手術後の感染(SSI:手術部位感染)を予防する目的であらかじめ抗生物質を投与することを「予防的抗菌薬投与」といいます。 手術後にSSIが発生すると、入院期間の延長や医療費の増加につながるため、SSI対策は非常に重要です。 SSI予防の一環として、通常、手術開始前1時間以内に抗菌薬を静脈投与することが推奨されており、このタイミングで投与することで、十分な殺菌作用を示す血中および組織中の抗菌薬濃度を確保でき、効果的なSSI予防が可能となります。 |
|---|---|
| 投与率 | 全身麻酔手術で予防的抗菌薬が投与された手術のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬の投与が開始された手術の割合です。 |
| 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 |
| 1310 | 1297 | 99.01% |
当院の手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率は99.01%という結果となりました。
一般的には、手術開始前1時間以内に抗菌薬を投与することが推奨されていますが、バンコマイシンなど血中濃度の上昇に時間がかかる薬剤については、手術開始前1時間以内の投与では効果が不十分な場合があり、それより早いタイミングで投与を開始することが推奨されています。
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡について、患者数と発生率を集計しています。
この指標は、入院中に褥瘡が発生した患者数となります。入院時既に褥瘡を保有している患者(持ち込み褥瘡患者)や、同一日に入退院された患者は集計対象外としています。
■DESIGN-R®分類2020・・・日本褥瘡学会によって定めた褥瘡状態の評価スケールであり、Depth(深さ)、Exudate(滲出液)など、計7項目から構成されています。中でも、褥瘡の進行度を示し、治療方針の決定において重要な指標となる「Depth(深さ)の分類」は、特に重要な評価項目の一つです。
| Depth(深さ)の分類 | 皮膚損傷の状態 |
|---|---|
| d0 | 発赤のない、健康な皮膚 |
| d1 | 発赤のみ |
| d2 | 真皮までが損傷された状態 |
| D3 | 皮下組織まで損傷され、皮下脂肪が露出した状態 |
| D4 | 皮下組織が全て欠損し、筋肉や骨が露出した状態 |
| D5 | |
| DTI | 軽症に見えるが深部組織にダメージが及んでいる可能性がある状態 |
| U | 表面が壊死組織で覆われており正確な深達度が判定できない状態 |
【用語について】
| 褥瘡(じょくそう) | 褥瘡は「床ずれ」とも呼ばれ、長時間にわたって同じ部位が圧迫されることで血流が遮断され、皮膚組織が壊死してしまうことによって発生する傷(潰瘍)のことです。 特に、入院中や寝たきりの状態が続く患者さんではリスクが高く、褥瘡が悪化すると感染症のリスクが高まり、深刻な合併症を引き起こす可能性もあります。創傷が深くまで進行すると、治療が非常に難しくなるため、早期発見・早期治療が極めて重要とされています。 |
|---|---|
| 発生率 | 集計対象外患者を除く入院患者延べ数のうち、d2以上の褥瘡が発生した患者さんの割合です。 |
| 退院患者の在院日数の総和もしくは除外条件に該当する患者を除いた入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 |
| - | - | - |
褥瘡は、身体的な苦痛だけでなく、ADL(日常生活動作)の低下や社会復帰の遅れにもつながる重要な問題であるため、当院では褥瘡予防対策に積極的に取組んでいます。
その結果、d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生患者数が10症例未満であり、発生率は0.02%と非常に低い水準にとどまっています。
また、上記データには反映されておりませんが、d2以上の褥瘡が発症した患者さんの平均年齢は71.63歳と高齢であったことから、免疫機能が低下した高齢者や慢性疾患を抱える患者さんは、褥瘡リスクが高まることが分かる結果となりました。
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメントについて、患者数と実施割合を集計しています。
【用語について】
| 栄養アセスメント | 栄養アセスメントは、患者さんの「栄養状態を多角的に評価」することを指し、適切な栄養診断とその後の介入につなげるために、欠かせない重要なプロセスです。 病気と治療は、単に薬や手術で対処するものではなく、「栄養」という土台の上に成り立っており、栄養管理の質は 治療の質を大きく左右します。 特に、65歳以上の高齢患者では、低栄養やサルコペニアのリスクが高く、入院時点ですでに筋肉量の減少や栄養不足が進行しているケースも少なくありません。したがって、入院早期(48時間以内)に栄養アセスメントを実施し、適切な介入につなげることが極めて重要とされています。 |
|---|---|
| 実施割合 | 65歳以上の患者のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者さんの割合です。 |
| 65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 |
| 1266 | 1208 | 95.42% |
当院では、65歳以上の患者の入院早期(48時間以内)の栄養アセスメント実施割合は95.42%という結果となりました。
今後も患者さん一人ひとりに合わせた適切な栄養管理を行うため、早期介入に努めていきます。
身体的拘束を実施した患者について、拘束日数と実施率を集計しています。
【用語について】
| 身体的拘束 | 身体的拘束は、抑制帯等、患者さんの身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に身体を拘束し、運動を抑制する「行動制限」のことです。しかし、このような行為は、患者さんの意思に反して自由を奪うことで、人権や尊厳を損なうおそれがあるとして、大きな問題となっています。そのため、患者さんの生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束は原則として行わないこととされており、拘束の最小化に向けた取組みが重要となっています。 |
|---|---|
| 実施割合 | 在院日数の合計のうち、身体的拘束の合計日数の割合です。 |
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) | 身体的拘束の実施率 |
| 30030 | 1597 | 5.32% |
当院の身体的拘束実施率は5.32%となりました。
身体的拘束は、倫理面や身体面など様々なリスクを伴うため、原則として、緊急やむを得ない場合を除き「身体的拘束を行わない方針」のもとで診療・看護を提供しています。
また、職員一人ひとりが身体的拘束の弊害を正しく理解し、拘束廃止の意識を持って対応するよう努めています。
- 2025/09/24
- データ更新
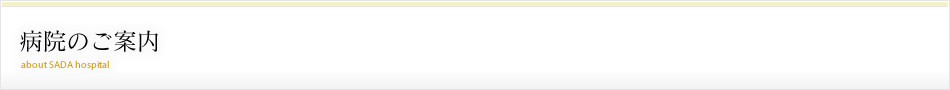



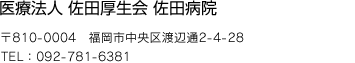

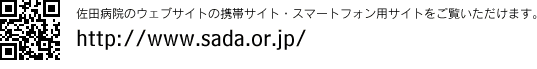
主な診療科は外科、整形外科、内科、消化器内科であり、入院の大半は手術目的です。
入院患者全体の平均年齢は61.19歳、うち約4割を60~70代が占めるとはいえ、20~60代のいわゆる現役世代も多く、都市部に立地する地域特性を反映する急性期病院です。
また後述する外科の胆のう関連疾患の患者平均年齢は57.03歳、多汗症は同27.93歳、整形外科の腰椎椎間板ヘルニアも同46.18歳と平均年齢の低い症例が多いのも特徴です。